※結論
フィンペシアの副作用は私の場合「ゼロではないが、調整すれば60代でも無理なく続けられる範囲」でした。
こんにちは、沢田です。
「フィンペシアって、副作用が怖い…」
これ、AGA治療を始める人が一番気になるところだと思います。
私も60代でフィンペシアを使い始めたとき、性欲の低下やむくみっぽさを感じたことがありました。
ただ、ここで大事なのは――
副作用は“ゼロか100か”じゃないということです。
この記事では、私の実体験として
- どんなタイミングで何が起きたか
- 「フィンペシア単体なのか/併用薬の影響なのか」の考え方
- 私が続けるためにやった工夫(服用間隔・飲み方・生活習慣)
を、できるだけ分かりやすくまとめます。
※体調に不安がある方は、自己判断せず医師に相談してくださいね。
フィンペシアで感じた副作用とは?
私がAGA対策としてフィンペシアを使い始めたのは、60歳を過ぎてからです。
「本当に効くのかな…」と半信半疑でしたが、ミノキシジル(内服)との併用も含めて、髪のハリが戻る感覚はありました。
一方で、体の変化もゼロではありませんでした。
ただし注意点として、私の場合は“併用”していたので原因の切り分けが難しいです。
この記事ではその前提も含めて、正直に書きます。
最初に気づいた副作用は「性欲の低下」
私が最初に「あれ?」と思ったのは、性欲の低下でした。
正直に言うと、毎日強く意識していたものが、
数日に一度くらいでも気にならない状態になっていました。
ただ、ここで強調したいのは、
「生活に支障が出るほどではないけど、変化としては分かる」
このくらいの感覚だったことです。
もうひとつ気になったのが、朝のむくみっぽさです。
特に足首あたりが「いつもより張ってる?」と感じる朝がありました。
ただし、ここは大事なのでハッキリ書きます。
むくみはミノキシジル内服側で言われることもあるため、
私のケースでは「フィンペシアだけが原因」と断定できません。
なので私は、
「原因を決めつけず、負担を減らす方向で調整する」
この考え方に切り替えました。
(※むくみが強い・息切れ・動悸などがある場合は、すぐ医師に相談推奨)

飲み合わせに注意したこと
私は普段から血圧の薬を飲んでいるので、飲み合わせはかなり慎重になりました。
自己判断で進めるのは怖かったので、薬剤師に相談して「まずは時間をずらす」ことを徹底しました。
副作用対策って、特別なことよりも
“変化が出たときに戻せる設計”にしておくほうが大事だと感じています。
朝はフィンペシア、夜は他の薬に分ける
私がやったのは、シンプルに 時間帯を固定して分ける ことでした。
- フィンペシア:朝食後
- それ以外:夕方〜就寝前
これだけでも、体の感覚として「今日はラクかも」と思う日が増えました。
(※あくまで私の体感です)
AGA治療に使う薬の比較体験はこちらの記事へ
公式サイトはこちらです
▼ ▼
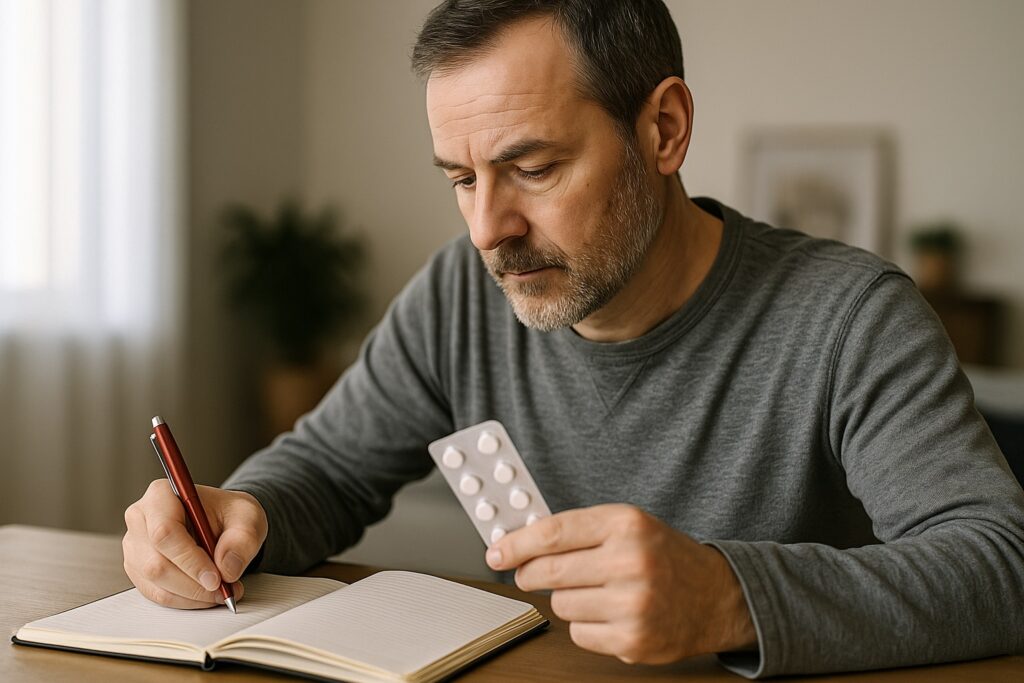
私なりの副作用対策と継続の工夫
副作用が怖いからといって、いきなり「完全にやめる」選択をすると、
今度は抜け毛が戻るリスクが出てきます。
私が選んだのは、
“やめる”ではなく“負担を減らして続ける” という方向でした。
2日に1回、または3日に1回の服用に変更
私が一番効いたと感じた工夫は、服用間隔の調整です。
- 毎日 → 2日に1回
- 状態によって → 3日に1回
この形にしてから、私の場合は
副作用っぽさが落ち着いた感覚がありました。
もちろん、本来は毎日が基本だと思います。
ただ、私のように「続けるのが苦しい」状態なら、
医師に相談しつつ“続けられる形”を探すほうが現実的だと感じました。
「副作用を理解しておくことは大事ですが、それだけでなく“治療を続ける上で後悔しないための考え方”も欠かせません。私が学んだ3つのポイントはこちらで紹介しています
👉 AGA治療で後悔しないための3つのポイント|60代の私が学んだ教訓」
ここまでで副作用の実態は理解いただけましたか?
続いて、私が実際に向き合った症状と対策をより具体的にご紹介します。
私がフィンペシアを選んだ理由と、続ける工夫
私がフィンペシアを選んだ理由は、正直に言うと コストです。
プロペシアは安心感がある反面、長期で考えると負担が大きい。
その点、フィンペシアは
「同成分(フィナステリド)で続けやすい」
と感じました。
そして私の中では役割を分けています。
- ミノキシジル:生やす側(実感しやすい)
- フィンペシア:守る側(抜け毛を抑える)
この“役割分担”で考えると、
フィンペシアは「主役」ではなくても、
続ける価値はあると私は感じています。
むくみ対策にウォーキングを追加
むくみっぽさが気になったときに、私が追加したのが 軽いウォーキングでした。
- 朝 or 夕方に15分
- できる日は少しだけ長め
「劇的に変わった!」ではないですが、
体が軽い日が増えた感覚はありました。
(※ここも私の体感です)
ミノキシジルとの併用体験はこちら
公式サイトはこちらです
▼ ▼

ここまで読んでいただきありがとうございます。副作用の実態はイメージできましたか?
最後に、私が実践した対策を振り返ります。
フィンペシアの副作用と向き合いながら続けるコツ
私の結論はこれです。
- 副作用は“ゼロ”とは言い切れない
- でも、自己判断でやめると 抜け毛が戻るリスクがある
- 大事なのは「無理なく続く形」を作ること
私の場合、効いたのはこの2つでした。
- 服用間隔を調整する(毎日→2〜3日に1回)
- 軽い運動で体調を整える(ウォーキング)
副作用が不安な人ほど、
「やめる」より先に「調整する」を知っておくと、後悔が減ると思います。
よくある質問(FAQ)
Q1. フィンペシアの副作用は全員に出ますか?
A. 出方には個人差があります。まったく感じない人もいれば、性欲低下や体の違和感を感じる人もいます。大切なのは「変化に気づけること」と「無理せず医師に相談できること」です。
Q2. 性欲低下が気になります。続けても大丈夫ですか?
A. 私の場合は“生活に支障が出るほどではないが変化は分かる”程度でした。気になるときは、服用のタイミングや間隔を見直したり、医師に相談して調整するのが安心です。
Q3. むくみはフィンペシアの副作用ですか?
A. 私は併用していたため断定できませんでした。むくみは別の要因でも起こることがあるので、強いむくみや息切れ・動悸などがある場合は、早めに医師へ相談してください。
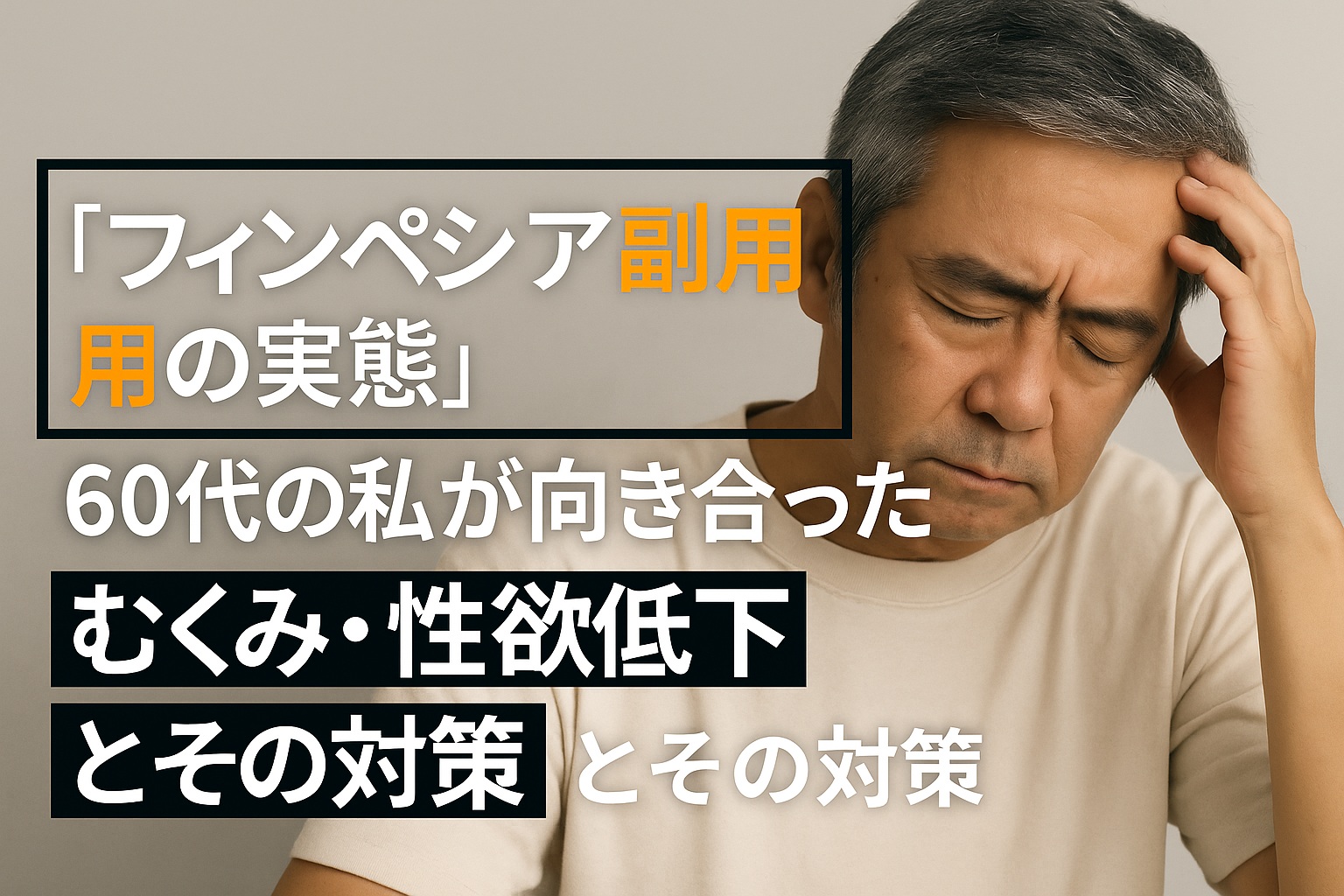
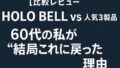
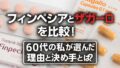
コメント